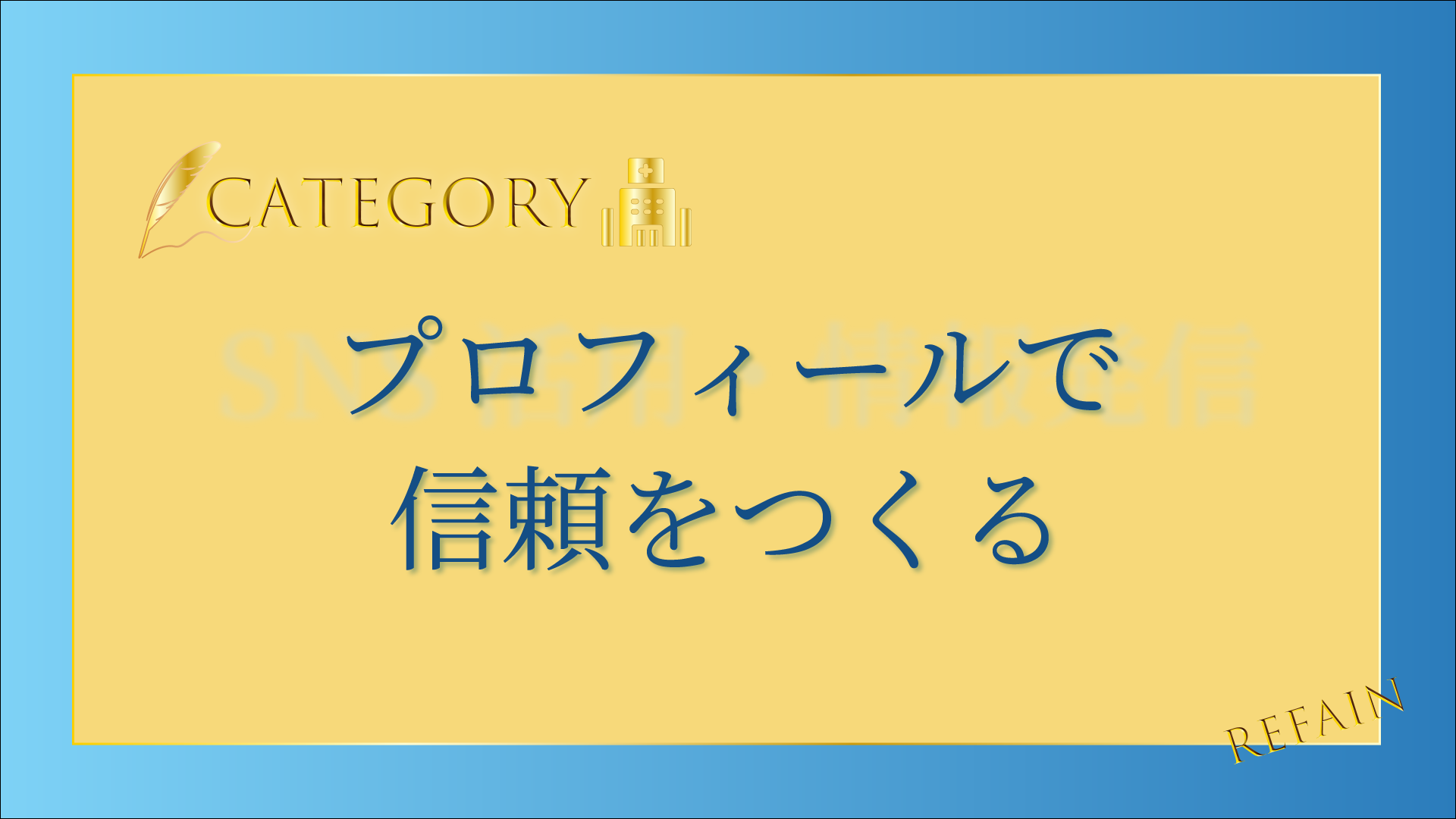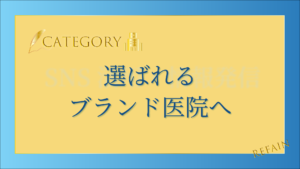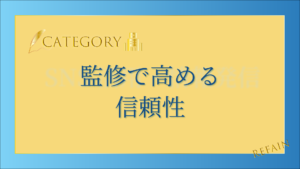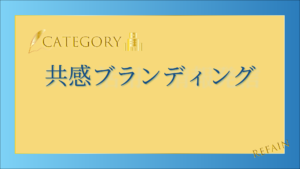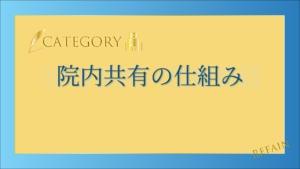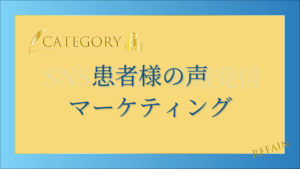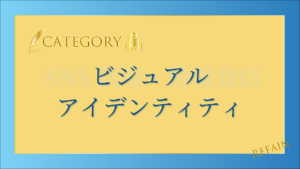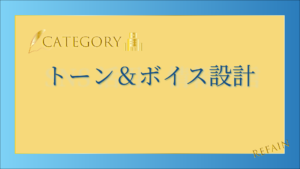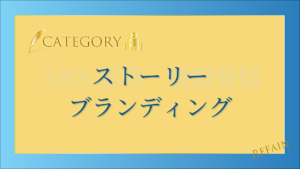1.なぜ「人柄」が伝わるプロフィールが重要なのか
 院長
院長プロフィールって、経歴を並べるだけではダメなんでしょうか?



経歴は大切ですが、患者様が知りたいのは「この先生はどんな人か」。
つまり、共感と安心を感じられるかどうかです。
“どんな考えで診療しているのか”“どんな患者様を助けたいのか”が伝わることで、初診時の心理的ハードルが下がります。
共感:「この先生なら話せそう」と思える。
信頼:治療方針の背景が理解できる。
記憶:顔とエピソードが印象に残る。
患者様は「専門家」よりも「理解してくれる人」を選びます。
プロフィールは、医院の“入口”として信頼構築を支える大切なパーツです。
2.プロフィール構成の基本5パート(読まれる順番を意識)



どんな順番で書けば、最後まで読んでもらえるんでしょう?



患者様は最初の3秒で「読むかどうか」を決めます。 ですから、最初に“想い”が伝わる構成にしましょう。以下の5パート構成がおすすめです。
- ① 導入文:「はじめまして」+診療姿勢の一言。例:「患者様の笑顔を守ることが、私の原点です。」
- ② 経歴:大学・勤務歴・専門分野。年号をすべて載せず、簡潔に。
- ③ 想い:なぜ歯科医になったのか、どんな患者様を支えたいのか。
- ④ ビジョン:医院の未来像。「痛みの少ない治療を当たり前に」「地域で一番話しやすい歯医者に」など。
- ⑤ プライベート:趣味や家族の話で“親しみ”をプラス。例:「休日は子どもと釣りへ」「コーヒーを淹れるのが日課です」
プロフィールは「信頼+共感+記憶」で構成します。 読み手に“安心”を届けるトーンを意識し、堅苦しさよりも“人間らしさ”を大切にしましょう。
3.「経歴より想い」で伝えるライティング術



資格や実績ばかり並べてしまうんですが、どうすれば「想い」を伝えられますか?



「なぜその行動をしているのか」を書くことです。 たとえば「痛みの少ない治療を心がけています」ではなく、 「過去に治療が怖くて通えなかった経験があるため、同じ思いをさせたくない」という“背景”を入れる。 すると一気にストーリーになります。
患者様は技術よりも“信頼”で医院を選びます。数字ではなく心のエピソードを語ることが、選ばれる医院への第一歩です。
4.写真・ビジュアルで印象を2倍に(視覚的信頼の法則)



プロフィール写真って、どんな基準で撮ればいいんですか?



第一印象を決める要素は、実は“表情”です。 白衣と清潔感はもちろん、柔らかな笑顔・自然光・明るい背景が理想。 写真が硬いと「話しかけづらい先生」と感じられることもあります。 また、診療中の姿・患者様と話す瞬間など、動きのある写真を1枚入れると人柄が伝わります。
明るい背景:白・水色・木目調など、医院の清潔感を表す色を。
表情:口角を軽く上げて目線をカメラに。優しい笑顔がベスト。
動きのあるカット:説明や診療シーンを加えて「仕事への誠実さ」を伝える。
患者様は無意識に「写真の印象」で信頼を判断します。 暗い照明や険しい表情は避け、#F7FAFC系の明るさを意識しましょう。
5.NG/OK表現(そのまま使えるテンプレ付き)
NG例:距離がある・一般的すぎる表現
- 「○○大学卒業後、△△医院を経て開業いたしました。」
- 「常に最新の技術を取り入れ、地域に貢献しております。」
OK例:人柄+想いが伝わる表現
- 「幼い頃、治療が怖くて歯医者に行けなかった経験から、“痛みの少ない治療”を追求しています。」
- 「仕事や育児で忙しい方にも通いやすいよう、平日19時まで診療を続けています。」
- 「“怖くない・通いやすい歯医者”を目指し、今日も笑顔でお迎えしています。」
「どんな考えで診療しているか」が伝わる文章にすることで、読み手は「この先生なら大丈夫」と感じます。
6.SNS・院内掲示・求人票に応用(ブランディング一貫化)



プロフィールをSNSや院内にも使っていいんですか?



もちろんOKです! 同じ文をHP・SNS・求人票に掲載すると、医院の信頼が多点接触で強化されます。 「Instagramで見た言葉が院内にも書いてある」と気づいた瞬間、患者様は“本気の医院だ”と感じます。
プロフィールはブランディングの“中心の言葉”。媒体ごとに使い回すことで、医院のトーンが統一され、SEO的にもプラスになります(共起語が自然に拡散されるため)。
7.まとめ:プロフィールは“信頼の最初の一歩”
プロフィールは経歴より“想い”を伝える
導入→想い→ビジョン→プライベートの5構成
写真は自然光×笑顔×清潔感が基本
OK例に言い換え、共感を生む文章へ
同じ文をHP・SNS・院内掲示で反復
次回記事のお知らせ(⑤ “口コミ・紹介”につながる患者様との関係づくり)
次回は、信頼関係を深めて「口コミ・紹介」が自然に広がる仕組みづくり。
院長の姿勢・スタッフ対応・患者満足度アンケートの活かし方を紹介します。