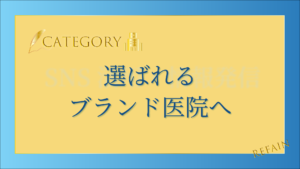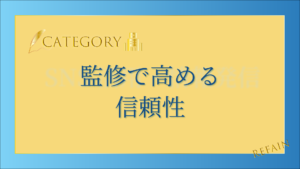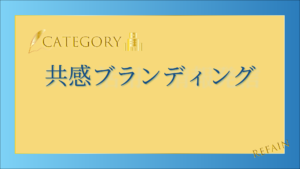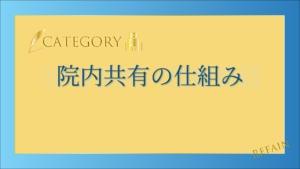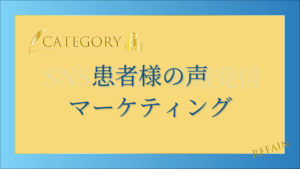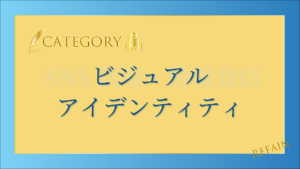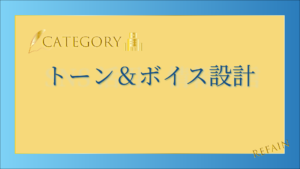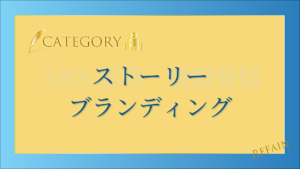1.E-E-A-Tとは?(医療サイトに求められる4要素)
 院長
院長E-E-A-Tって聞いたことはありますが、どういう意味なんですか?



4つの単語の頭文字をとった考え方です。
E:Experience(経験)
E:Expertise(専門性)
A:Authoritativeness(権威性)
T:Trustworthiness(信頼性)
Googleは「お金・健康」に関わる情報(YMYL)を、これらの観点で評価します。
つまり“どんな立場の人が、どんな経験をもとに語っているか”がとても重要なのです。
この考え方はSEOの世界だけでなく、患者様の安心感や納得度にも直結しています。 医療サイトでは、どんなに綺麗なデザインでも「誰が伝えているのか」が不明瞭だと不安を与えます。 逆に、院長の顔や経歴、理念、患者様との実際のエピソードが載っていれば、瞬時に“信頼の温度”が上がります。
- 経験:治療経験・症例実績・現場の声を明示
- 専門性:資格・所属学会・専門医制度など
- 権威性:メディア掲載・講演・論文など第三者評価
- 信頼性:運営情報・実名・正確なデータ
これら4つをページの中で自然に表現できると、検索エンジンだけでなく、人の目にも「信頼できる医院」として映ります。 では、具体的にどんなページ構成でE-E-A-Tを伝えると効果的なのでしょうか。
2.プロフィールが“信頼の起点”になる理由



プロフィールって経歴を書くだけでは足りませんか?



足りません。 患者様は経歴よりも人柄を知りたいのです。 どんな思いで診療をしているのか、なぜこの道を選んだのか。 その背景に共感できたとき、はじめて「この先生に診てもらいたい」と感じます。
プロフィールページは、いわば医院の“信頼の玄関”。 求人でいえば会社案内、ブランドでいえば企業理念のようなものです。 経歴だけではなく、想い・人柄・日常の表情を言葉と写真で見せることで、共感が生まれます。
① 想い(理念・原点・診療姿勢)
② 経歴(大学・勤務歴・所属学会など)
③ 写真(自然な笑顔+診療風景)
これらが揃うことで、検索エンジンにも“実在性の高い人物”として評価されやすくなります。 さらに、プロフィール文の中に「治療方針」「対応方針」など具体的な行動指針を入れると、SEO的にもテーマの一貫性が強化されます。
3.症例紹介でE-E-A-Tを強化する(経験×信頼)



症例を載せるとき、どんな点に注意すればいいですか?



最も重要なのは「誇張しない」ことです。 症例紹介は実績を示す手段ですが、患者様が誤解しないように条件とリスクを明記することが大前提です。
また、症例写真のビフォーアフターを並べるときは、撮影条件を統一し、明るさや角度が変わらないようにするのが鉄則です。 ほんの少しの差で、印象がまったく違って見えることもあります。 症例文には「治療期間」「使用した素材」「費用の目安」などを具体的に記載し、透明性を高めましょう。
- OK:治療法・リスク・費用を明記し、個人差の注記を添える
- NG:「必ず治る」「完全に白くなる」など断定的表現
- OK:本人同意を得た実際の症例を使用
- NG:医師名や出典が不明な画像を流用
症例紹介は、単に「治した結果」を見せる場ではなく、医院の考え方を伝える場所です。 “どう治したか”よりも、“なぜそうしたのか”を語ることで、読んだ人の共感と信頼を得られます。
4.実在性の証明で“信頼”を底上げする



「実在性」って、何を指すんでしょう?



Web上では、誰でも情報を発信できる時代だからこそ、 “本当に存在する医院”であることをきちんと示すことが重要です。
- 運営者情報(所在地・責任者・電話番号)を掲載
- スタッフ紹介・院内写真・アクセス情報の充実
- プライバシーポリシー・特定商取引法表記の明示
- SNS・Googleビジネスプロフィールとの情報整合性
これらを整えることで、検索エンジンは「信頼できる実在サイト」と判断します。 患者様も「本当に存在する医院」と安心して来院を検討できます。
5.外部評価で“権威性”を補強する(第三者の声)
第三者による評価は、自分で語るよりも強い説得力を持ちます。 「所属学会」「専門医資格」「講演歴」「メディア掲載」「紹介状の発行医院」などを整理して掲載しましょう。 とくに専門医番号の明記や学会ロゴの使用は、信頼度を高める効果があります。
- 所属学会・認定医・専門医番号を公式に記載
- 講演・取材・メディア掲載実績を一覧で掲載
- 地域連携病院・紹介医リストをわかりやすく提示
- 患者様の声や体験談(同意済み)を引用
また、Googleビジネスプロフィールのレビューをサイトに埋め込むことで、実際の評価がリアルタイムに伝わります。 外部の声があるだけで、サイト全体の信頼度が大きく上がります。
6.E-E-A-Tを高めるページ構成チェックリスト
- 院長名・写真・資格を明示しているか
- 治療方針に「想い・根拠・証拠」が揃っているか
- 症例は条件と個人差を必ず記載しているか
- 外部評価(学会・紹介・メディア)を掲載しているか
- 運営者情報・法的表記を明確にしているか
これらをチェックして整えるだけでも、サイト全体の信頼性は大きく向上します。 E-E-A-TはSEO対策というより、「選ばれる医院になるための信頼設計」と捉えるのがポイントです。
7.まとめ:E-E-A-Tは「人」と「実在」で伝わる
医療ブランディングの本質は、肩書きや数字ではなく、“誠実に伝える姿勢”です。 経験を重ねた医師の言葉には、自然と信頼が宿ります。 E-E-A-Tを意識してプロフィールと症例を整えることは、患者様との“信頼の対話”を始める第一歩です。
次回記事のお知らせ(⑨ Googleビジネスプロフィール&クチコミ運用)
次回は、オンラインでの信頼構築をさらに深めるステップ。 Googleビジネスプロフィールを活用して、クチコミ・投稿・写真から“リアルな信頼”を育てる方法を紹介します。