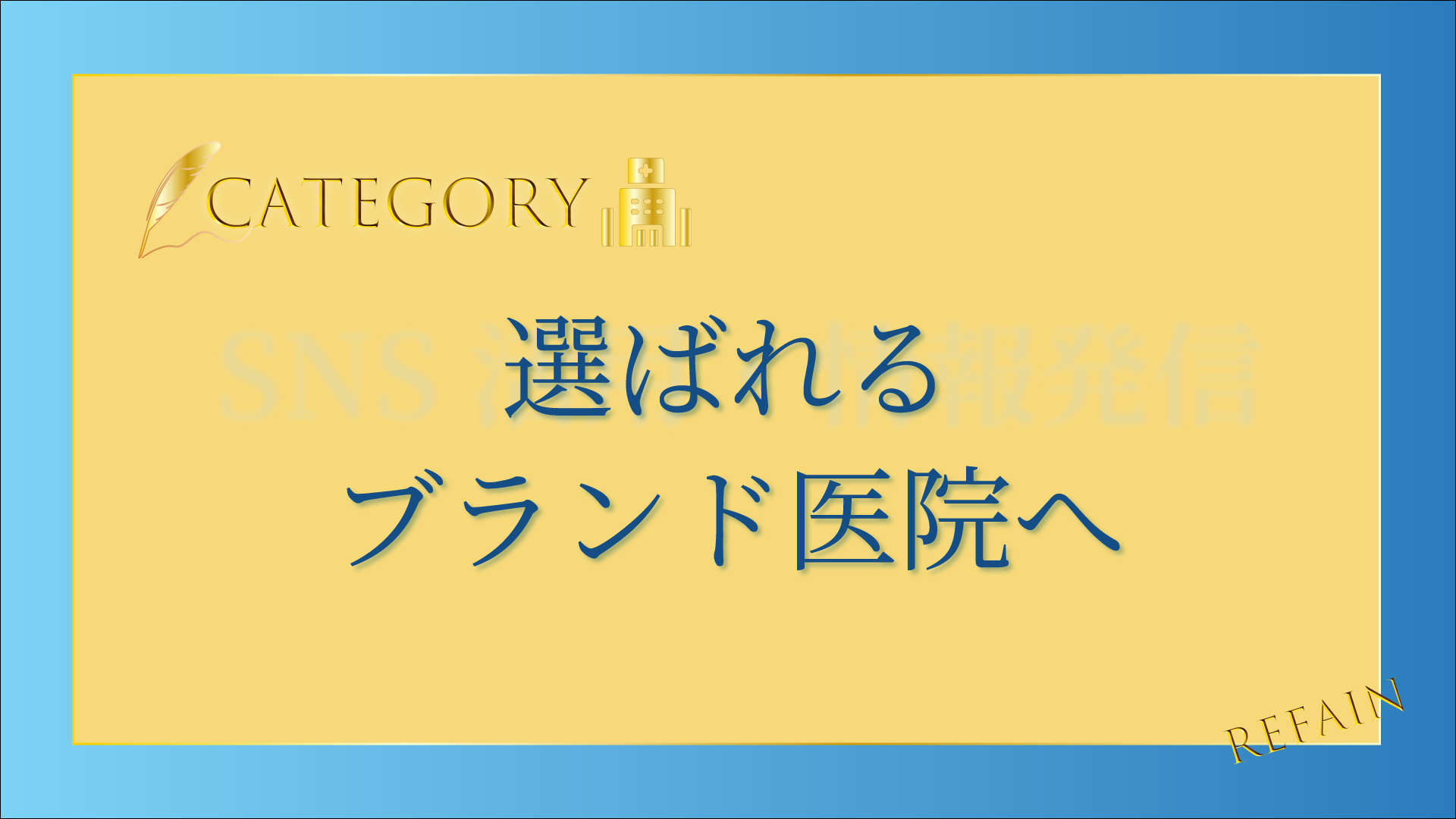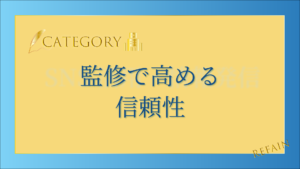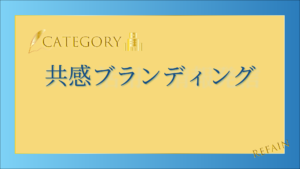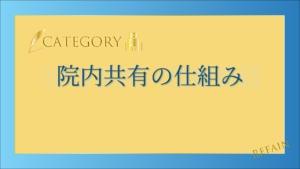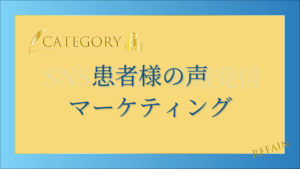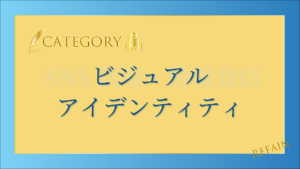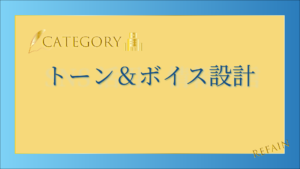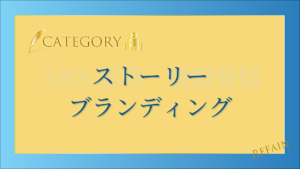1.理念を「見える形」にする
まず大切なのは、医院の理念を“見える化”すること。
言葉・デザイン・行動・空間を通して理念を体現することで、患者様や地域社会に「何を大切にしている医院か」が伝わります。
ホームページやパンフレットに理念を掲載するだけでなく、スタッフの行動指針としても共有しましょう。
2.患者様の体験価値を高める
医院のブランドは、患者様の体験から生まれます。
診療だけでなく、受付対応・説明・空間づくり・アフターフォローまで、すべてがブランド体験です。
「この医院なら安心できる」と思ってもらえる小さな積み重ねが、信頼を生みます。
3.地域に寄り添う情報発信を行う
地域密着型の医院ほど、地域住民とのコミュニケーションがブランド力になります。
季節の健康情報・地域イベントへの参加・学校や企業との連携など、日常的に地域と関わる発信を意識しましょう。
SNSやLINE公式なども、患者様との関係を育てる重要なツールです。
4.「信頼の証」を積み重ねる
口コミ、監修、掲載メディア、学会所属などは、すべて医院の信頼を示す“証”になります。
とくに監修・取材・患者様の声などは、第三者視点で信頼を補強できる強力な要素。
これらを整理し、公式サイトやパンフレットにわかりやすく掲載することが重要です。
5.一貫したデザインとトーンを保つ
ロゴ、色、書体、言葉の使い方など、医院を表す「トーン&マナー」が統一されていると、安心感と信頼感が生まれます。
Web・紙・看板・SNSのすべてで一貫性を保つことが、ブランドの成熟度を高めます。
6.スタッフ全員でブランドを体現する
どれほど理念が素晴らしくても、実際に患者様に接するのはスタッフです。
「医院らしさ」を共有し、日々の行動や言葉づかいの中で体現することが、ブランディングの核心です。
スタッフ全員がブランドの“語り手”になれるような教育・共有体制を整えましょう。
7.継続的な改善と振り返りを行う
ブランドは「作って終わり」ではありません。
アクセス解析やアンケート、口コミなどを定期的に確認し、改善を続けることでブランドが磨かれていきます。
1年ごとにブランドレビューの時間を設けるのもおすすめです。
8.デジタルとリアルをつなぐ
ホームページやSNSなどデジタルの印象と、医院に来院した際のリアルな印象が一致していることが大切です。
Web上での期待を裏切らない“実体験”を提供することで、リピーターが増え、紹介も生まれます。
9.地域との共創を意識する
医院単体ではなく、地域社会全体の健康づくりを支える存在になること。
地域の学校・自治体・企業・福祉施設などと連携する活動は、「地域に必要とされるブランド」の証です。
10.“想い”を語り続ける
ブランドの原点は「想い」です。
なぜこの地域で開業したのか、どんな患者様を支えたいのか──その想いを言葉とデザインで伝え続けることが、最も力強いブランディングです。
ぱそあんのまとめ
- 理念・デザイン・行動が一致すると信頼が生まれる
- 体験・共感・継続改善がブランドを育てる
- 地域とのつながりが医院を「選ばれる存在」に変える
- “想いを語り続ける医院”こそ、真のブランド医院
💎 最後に
ブランディングとは、見た目を整えることではなく、医院の「想い」と「行動」を一致させること。
100本のテーマを通して目指してきたのは、“地域の中で信頼され続ける医院”という形です。
これからも、医療を通じて人と地域をつなぐ医院が増えることを願っています。