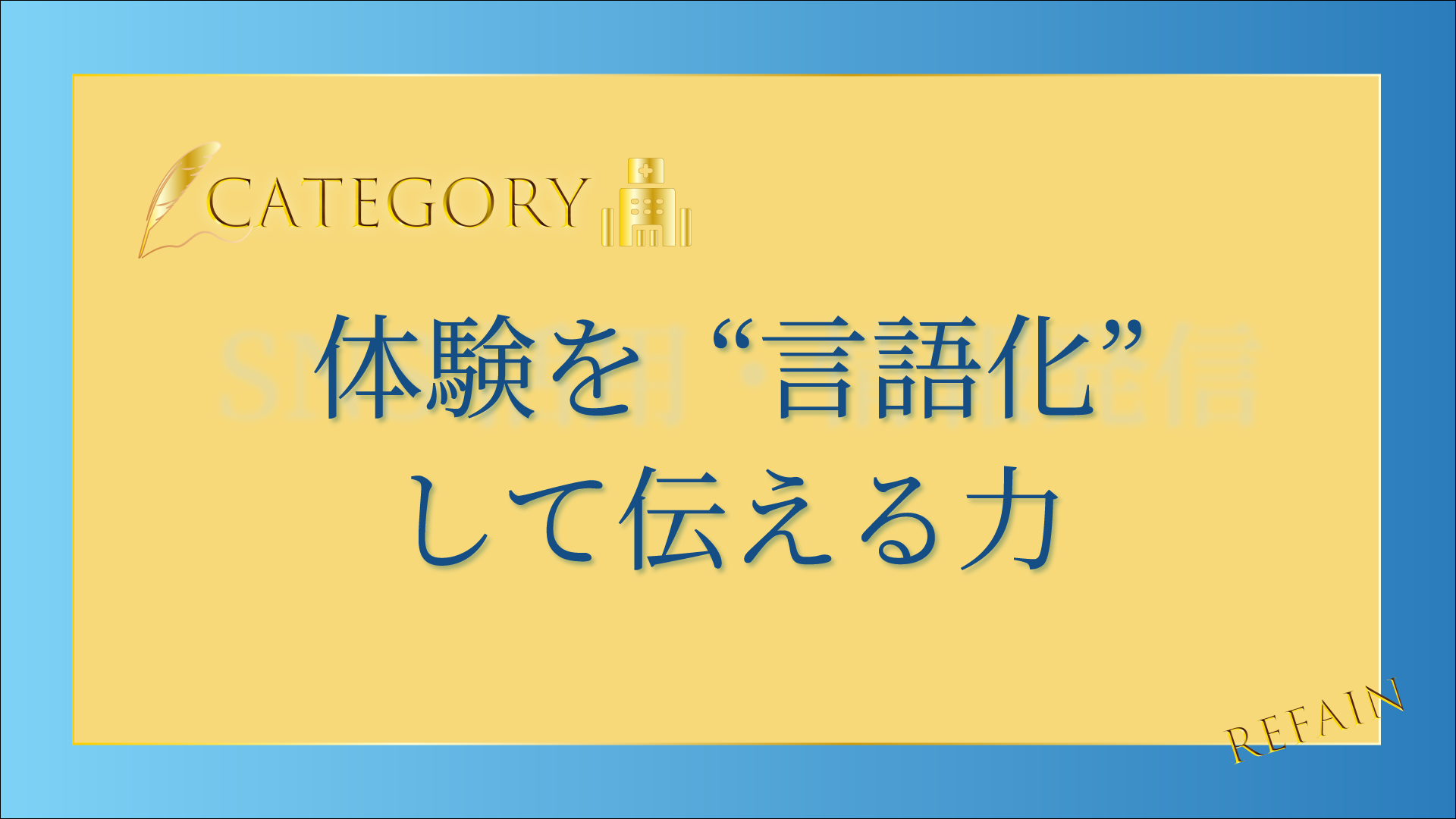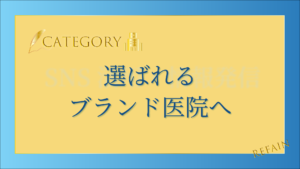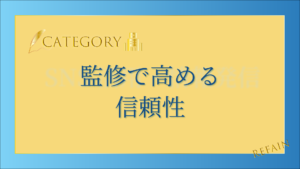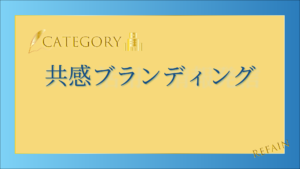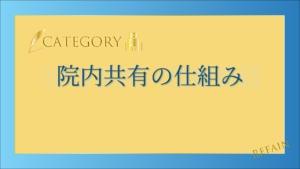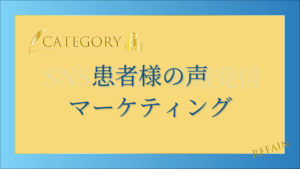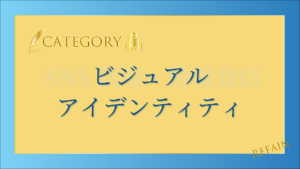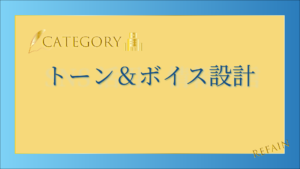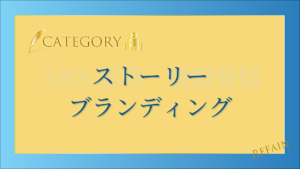1.「言葉」は院内ブランドの空気をつくる
どんなに優れた治療をしても、患者様は「説明」や「対応」の印象で医院を判断します。 受付スタッフの一言、カウンセリングでの話し方、治療前の説明――これらが医院のブランドを支える“声なき広告”です。
 院長
院長たしかに、同じ内容でも言い方ひとつで印象が変わりますよね。



そうなんです。言葉は、医院の理念を「感じさせる」ツールです。 たとえば「お待たせしました」と言うより「お時間をいただきありがとうございます」と伝える方が、丁寧で温かく感じられます。
ブランディングとは、「この医院の人はいつも感じがいい」と思ってもらう積み重ねです。 その基盤となるのが、スタッフ全員で共有された“言葉の基準”です。
2.受付スクリプトで「第一印象の統一」を図る
受付は、医院の“顔”です。
初診の電話対応や来院時の挨拶が、患者様にとって最初のブランド体験になります。
このタイミングでの印象が「信頼して任せられそう」につながるかどうかを左右します。
「お電話ありがとうございます。〇〇歯科クリニックでございます。」
「初めてのご予約でしょうか?」
「ご希望のお日にちをお伺いしてもよろしいでしょうか?」
「ありがとうございます。当日は5分前にお越しいただけますとスムーズです。」
一見ありふれた言葉でも、“順序”と“声のトーン”を整えるだけで、医院の印象は劇的に変わります。 スクリプトを共有する目的は、“誰が対応しても同じ安心感”を届けることです。
3.3分説明で「安心」と「納得」を両立させる
患者様は「何をされるかわからない」ことに不安を感じます。 短時間でも構いません。診療前に3分間の説明を加えるだけで、信頼度が格段に上がります。



3分で説明って、どこまで話せばいいんでしょう?



すべてを説明する必要はありません。 「これから行うこと」「理由」「終わったあとの状態」を簡潔に伝えるだけで十分です。 要は、患者様が“見通し”を持てることが大切です。
① 今回の治療内容を一言で説明(例:むし歯の神経を保護する治療を行います)
② なぜこの治療を選んだのか(例:歯をできるだけ残すためです)
③ 治療後の状態や注意点(例:麻酔が切れるまでお食事はお控えください)
この「3分説明」は、スタッフ教育にも活かせます。 新人スタッフが「どこまで説明してよいかわからない」と感じる場面で、このテンプレートを共有することで、医院全体の言葉の統一感が生まれます。
4.同意文テンプレで「誠実さ」を形にする
医療はリスクを伴う行為であり、誠実な説明と同意は信頼関係の根幹です。 同意文は法律的な役割だけでなく、医院の“誠意”を伝えるツールでもあります。
このたびの治療内容について、医師より十分な説明を受けました。
治療の目的・方法・期間・費用および予想されるリスクについて理解し、納得のうえで治療を受けることに同意します。
ご不明点があれば、いつでもご説明をお願いできることを確認しました。
文面はシンプルで構いません。 重要なのは、患者様が「押し付けられた」と感じない書き方にすること。 たとえば「同意します」だけでなく「理解し、納得のうえで同意します」と表現を加えることで、 相互の信頼を前提とした言葉になります。
5.「共通言語化」がスタッフ教育を変える
院内での言葉の共有は、スタッフ教育にも直結します。 スクリプトやテンプレートを「覚えるためのマニュアル」にせず、 「どうすれば患者様が安心するか」を考えるための“共通言語”として使うのがポイントです。



たとえば、新人スタッフにもわかるように伝えるには?



状況別に一言フレーズを共有するのが効果的です。
「少々お待ちください」ではなく「ご案内まであと数分お時間をいただきます」など、
“誠実で丁寧な日本語”を医院の共通ルールにすることです。
こうした共通言語がある医院は、どのスタッフが対応してもトーンが揃い、 患者様に「教育が行き届いている」という印象を与えます。 それがまさに院内ブランドの一貫性=安心感につながります。
6.体験と言葉をつなぐチェックリスト
- 受付・電話応対の言葉が統一されている
- 3分説明テンプレートをスタッフ全員で共有している
- 同意文は「理解と納得」を前提とした表現にしている
- 院内掲示やHPの文言も口調が一致している
- 言葉を通して「安心」「誠実」「温かさ」が伝わる
院内体験の言語化は、コストをかけずにできる“ブランディングの磨き上げ”です。 治療技術や設備投資と同じように、「言葉の質」を整えることが、医院の印象を大きく左右します。
7.まとめ:言葉が“医院の人柄”を伝える
医療ブランディングは、ロゴやデザインだけでは完成しません。 最も人の心に残るのは、日常の中で交わされる言葉のトーンです。 その一言一言が、医院の理念を具現化する「ブランド体験」になります。
院内の言葉を整えることで、患者様は「この医院は丁寧だ」「安心して任せられる」と感じます。 その積み重ねが、地域の中で長く愛される医院をつくる力になるのです。