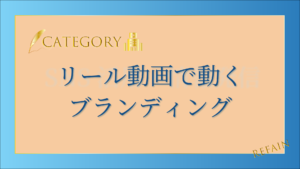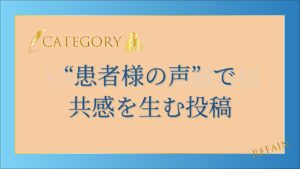1.なぜ医療SNSには“発信ルール”が必要なのか
医院のSNSは、発信内容がそのまま“信頼の証”になります。 しかし、何気ない一言や画像投稿が誤解を招いたり、医療広告ガイドラインに抵触することも。 特にスタッフが複数人で運用している場合は、投稿ルールを明確にしておくことが重要です。
 院長
院長スタッフが自由に発信しているけど、危険ですか?



“自由”は良いことですが、「どこまでOKか」の線引きが必要です。 ガイドライン違反や患者様の個人情報漏えいは、一瞬で信頼を失うリスクにつながります。
安心して運用を続けるためには、医院としての“公式ルールブック”を持つことが最初の一歩です。
2.SNS運用で注意すべき5つの禁止事項
- ① 治療効果の断定表現(例:「必ず治ります」「確実に白くなります」)
- ② 症例比較・他院との優劣表現(例:「地域で一番」「他より安い」)
- ③ 無断の患者写真・体験談の公開
- ④ 医療広告ガイドライン違反(料金・資格表記・誇大広告)
- ⑤ 個人や他職種への批判・揶揄投稿
SNSは“誰でも見られる医療広告”と考えましょう。 特に「治療効果」や「患者事例」は、掲載前に必ず院長確認を行う体制を整えることが大切です。
3.炎上を防ぐためのチェックリスト
「意図せず炎上した」というケースの多くは、確認不足が原因です。 投稿前に以下の3ステップでチェックを行いましょう。
- ① 内容チェック:医学的に正確か?誤解を生まないか?
- ② 写真チェック:患者様・スタッフの個人が特定されないか?
- ③ トーンチェック:言葉づかい・絵文字の使い方が医院らしいか?
さらに、定期的に「過去投稿の見直し」を行うことで、時代や方針の変化に対応できます。 数年前の投稿が思わぬ誤解を生むケースもあるため、アーカイブ管理も大切です。
4.写真・動画投稿の注意点(医療広告との境界)
写真や動画は医院の魅力を伝える強力な手段ですが、掲載には注意が必要です。 「院内の雰囲気を伝える写真」と「症例を紹介する写真」では、扱い方がまったく異なります。
- 院内写真・スタッフ写真 → 問題なし(表情や環境に配慮)
- 症例写真(治療前後) → 医療広告ガイドラインに基づき、条件・注意書きを必ず明記
- 患者様が写る場合 → 書面または電子同意を取得
- 動画内での説明 → 「効果を保証しない」などの補足文を入れる
たとえば「ホワイトニングで白くなりました!」とだけ書くのはNG。 「個人差があります」「〇回の施術を経て」など、条件を具体的に書くことがポイントです。
5.ネガティブコメント対応で信頼を守る



悪意あるコメントや口コミが来たときは、どうすればいいですか?



焦って反論しないことが第一です。 一度コメントが公開されると、削除よりも「対応の仕方」が見られます。 誠実に返信することで、逆に好印象を与えられることもあります。
- ① 感情的に反応しない:冷静に対処する
- ② 事実確認を行う:スタッフ間で共有して再発防止を考える
- ③ 公開コメントは丁寧に返信:「貴重なご意見ありがとうございます」で締める
口コミやコメントは、医院の改善ポイントを知る機会でもあります。 対応の姿勢こそが、医院の誠実さを示す「もう一つのブランディング」になります。
6.リスク管理のための“2人体制チェック”
SNS投稿は、できる限り2人体制でのダブルチェックを行いましょう。 特にキャンペーン告知や症例紹介などは、 院長・スタッフ・広報担当の3者で確認できるとベストです。
- 投稿下書きを共有ツール(Googleスプレッドシートなど)に保存
- 公開前に担当者2名以上が確認
- 確認済み投稿には「OK」スタンプや署名を残す
この体制があるだけで、投稿ミス・表現トラブルをほぼ防げます。 “確認ルールがある医院”というだけで、内部の安心感も高まります。
7.まとめ:SNSの信頼は“正確さ×誠実さ”で育つ
SNSは「気軽なツール」でありながら、医院にとっては「信頼の窓口」。 投稿内容の一つひとつが、患者様からの信頼を育てます。 そのためには、正確・誠実・一貫の3つが欠かせません。
スタッフ全員が「発信の目的は信頼」と理解していれば、 炎上や誤解を恐れずに前向きな情報発信ができます。 安全で温かいSNS運用こそ、医療ブランディングの基盤です。
次回記事のお知らせ(⑧ 患者様との“信頼コミュニケーション”を深めるSNS活用)
次回は、SNSで患者様と信頼関係を築くための“コミュニケーションデザイン”を紹介。 コメント返信・DM対応・共感投稿など、医院SNSを“対話の場”に変える方法を解説します。