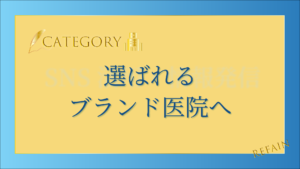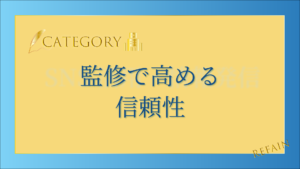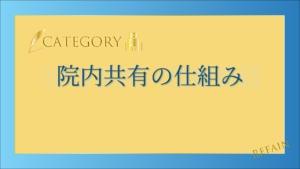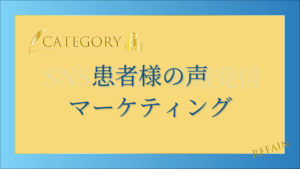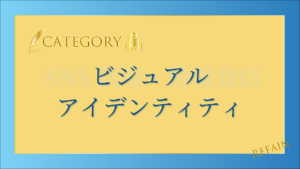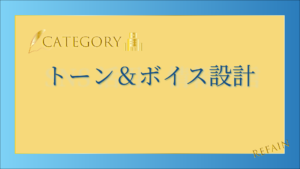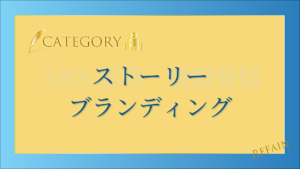目次
1.共感ブランディングとは?
共感ブランディングとは、広告や価格競争に頼らず、医院の想いと行動で信頼を築く戦略です。
「この医院は信頼できる」「また行きたい」と思ってもらう力は、広告よりも共感の積み重ねによって育ちます。
共感が生まれる3つの要素
- ① 誠実な姿勢(理念・一貫性)
- ② 開かれた発信(透明性・情報共有)
- ③ 参加型の関係性(地域・患者様との交流)
この3つが揃うと、患者様が「この医院を応援したい」と感じる“共感の循環”が生まれます。
2.理念を「共感の言葉」に変える
理念を掲げても、難しい言葉では伝わりません。
地域に共感されるためには、理念を「日常語」に翻訳することが大切です。
理念の“共感翻訳”例
- ・「地域医療への貢献」→「困ったときに最初に思い出してもらえる医院へ」
- ・「患者中心の医療」→「患者様の“生活”まで見つめた治療を」
- ・「チーム医療」→「スタッフ全員が同じゴールを見て動く」
共感される言葉には、専門用語よりも人の想いが感じられる言葉が必要です。
3.“地域とつながる発信”を育てる
共感を育てるには、地域との接点を増やすことが欠かせません。 ホームページやSNSでの発信も、単なるお知らせではなく「地域との会話」として考えましょう。
| 発信テーマ | 共感を生むポイント |
|---|---|
| 地域行事への参加 | 「○○フェスタに出展しました!」など、地域密着の活動報告 |
| スタッフの日常 | 働く人の表情やチームの雰囲気を見せる |
| 患者様との交流 | イベントや健康講座の開催レポート |
| ありがとうの声 | 患者様の感謝メッセージを紹介(匿名・許可の範囲で) |
「自分たちのこと」ではなく、「地域と共にある日常」を伝える発信が共感を呼びます。
4.地域との“リアルな接点”をつくる
共感は、リアルの場でも育ちます。 院内外の交流機会を設けることで、地域住民との信頼関係が深まります。
地域とのリアル接点づくりの例
- ・健康フェア・無料相談会を定期開催
- ・地元商店街や学校とのコラボイベント
- ・季節ごとの装飾や地域清掃活動への参加
- ・院内ギャラリーとして地域アートを展示
地域にとって「頼れる存在」から「親しみのある存在」へ。 この関係性の変化こそ、共感ブランディングの成果です。
5.共感の“測り方”と育て方
共感は数字で見えにくいものですが、患者様の語彙・行動・反応で確認できます。
| 観察ポイント | 共感が高まっているサイン |
|---|---|
| 口コミ・レビュー | 医院の理念に関連する言葉(“やさしい”“信頼できる”など)が増える |
| SNS反応 | 保存・シェア・コメントなどの共感行動が増える |
| 紹介率 | 「家族や友人からの紹介」が増加する |
| スタッフ発信 | スタッフが自発的に医院の取り組みを発信している |
このような「小さな共感の積み重ね」が、やがて“地域に根付くブランド”をつくります。
6.ぱそあんのまとめ
ぱそあんのまとめ
- 共感ブランディングは“広告ではなく関係性”で広がる
- 理念は専門語ではなく「人の言葉」で伝える
- 地域との接点をWebとリアルの両面で育てる
- 共感の指標は“口コミ・行動・紹介”で確認できる
次回シリーズ予告(99:ブランド監修・記事監修で信頼性を補強する)
次回は、専門家や第三者による「監修」を活用して、医院ブランドの信頼性をさらに高める方法を解説します。 E-E-A-T時代に欠かせない“監修ブランディング”の仕組みです。