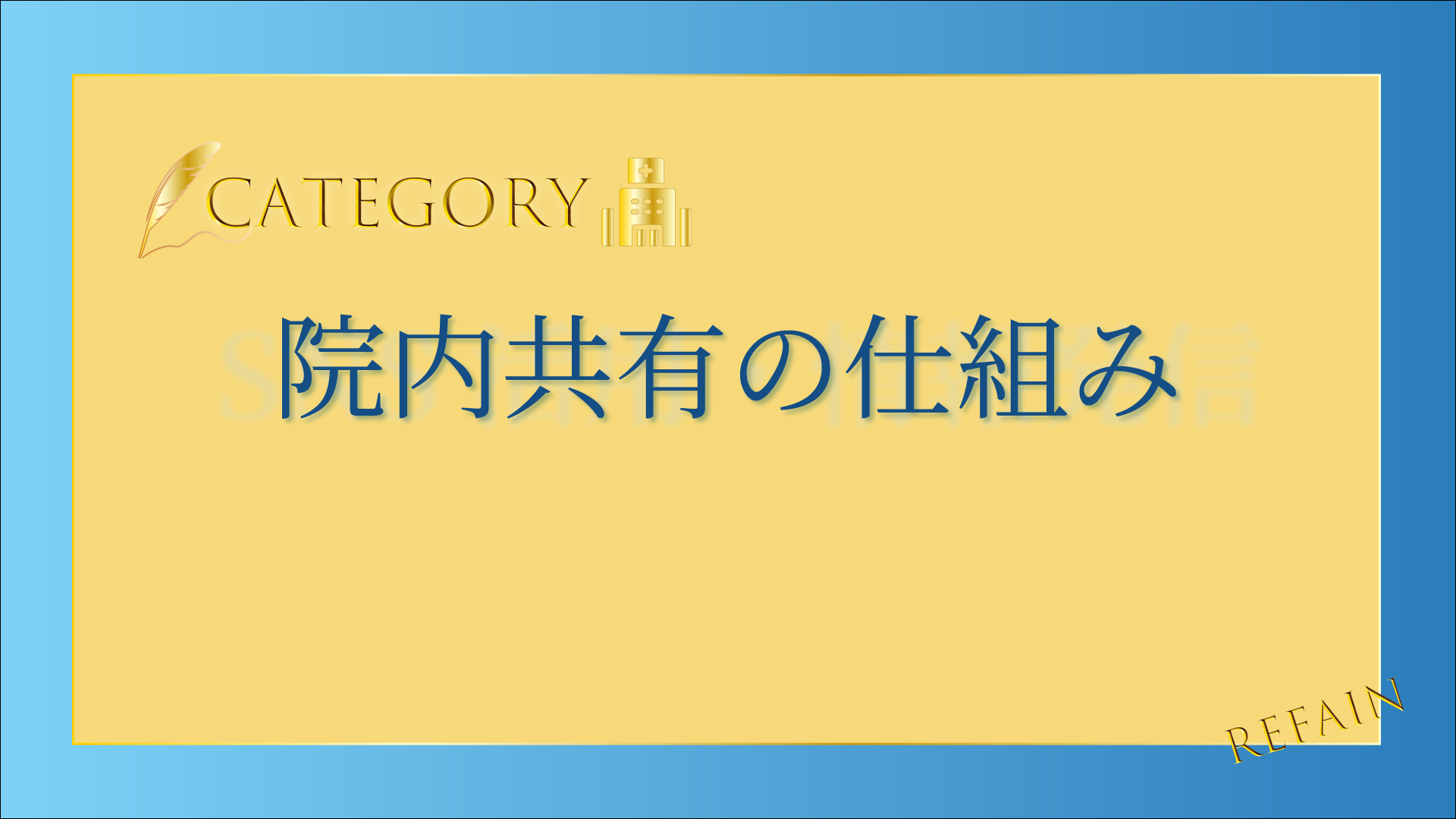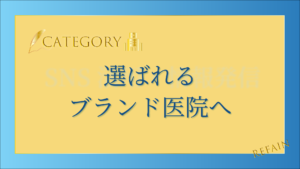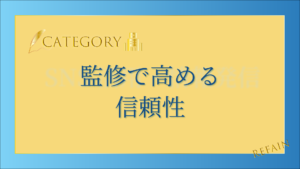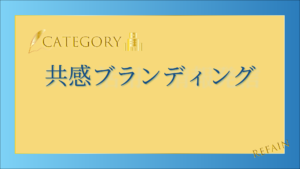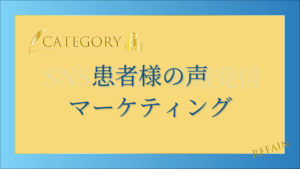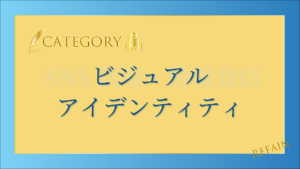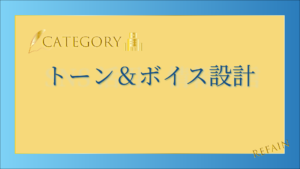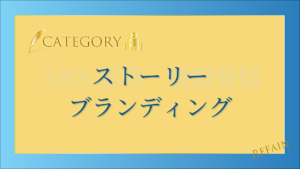目次
1.ブランド浸透の第一歩は“理念の翻訳”から
多くの医院で見られる課題は、「理念が抽象的すぎて行動に落とし込めていない」ということ。
たとえば「地域に貢献する」「患者様に寄り添う」といった理念も、具体的な行動に置き換えることで初めて共有できます。
理念の翻訳(例)
- ・「地域に貢献する」→ 地域行事や学校検診への積極的参加
- ・「患者様に寄り添う」→ 不安を感じたときは必ず声かけを行う
- ・「誠実な医療」→ 不明点をそのままにせず、確認してから対応
抽象的な理念を“行動で表現できる言葉”に変換する――これがブランド浸透の第一歩です。
2.日常の中でブランドを共有する仕組みをつくる
「ブランド共有」は会議や研修だけでなく、日々の業務の中で自然に行える仕組みを作るのがポイントです。
日常でできるブランド共有の工夫
- ・朝礼で「昨日の良かった対応」を共有
- ・週1回のミーティングで患者様の声を振り返る
- ・院内掲示に“理念カード”を設置し、いつでも確認できるように
- ・「接遇チェックシート」で行動の一貫性を確認
「共有=共有会議」ではなく、「文化として自然に育つ場づくり」こそが大切です。
3.スタッフが自分の言葉で語れる状態を目指す
本当のブランド浸透は、スタッフが「なぜこの医院で働くのか」「どんな想いで患者様に接しているのか」を自分の言葉で語れる状態です。
そのためには、トップダウンではなく対話型の共有を意識しましょう。
たとえば、
「この医院の“らしさ”って何だと思いますか?」
「患者様にどう見られたいですか?」
といった問いかけを通じて、スタッフ一人ひとりの言葉を引き出します。
その言葉を医院のステートメントやSNS投稿などに反映すれば、内側からの発信力が生まれます。
4.新人教育にもブランド要素を組み込む
新人スタッフが入るたびに同じ理念を1から説明していては非効率です。 そこで有効なのが、「ブランド教育マニュアル」の導入です。
ブランド教育マニュアルに含める内容
- ・医院の理念・ミッション・ビジョン
- ・患者様対応で大切にしている3原則
- ・言葉づかい・表情・姿勢など接遇ルール
- ・ブランドを感じる“成功エピソード集”
「理念=現場で使えるもの」として可視化すれば、新人でもすぐに“医院らしさ”を体現できます。
5.ブランド共有は“仕組み化”で継続する
一度共有して終わりではなく、仕組みとして続く形にすることが重要です。 医院の成長に合わせて、共有ルールを定期的に見直しましょう。
| 仕組み | 目的 |
|---|---|
| 四半期レビュー(15分会議) | ブランドの実践度を確認し、行動KPIを更新 |
| スタッフ表彰 | 理念行動を評価し、モチベーションUP |
| スタッフインタビュー | スタッフの声を発信に活用 |
| 院内報・SNS | スタッフの取り組みを外部にも共有 |
こうして“仕組みで続くブランド”が生まれれば、院長が不在でも医院の方向性はブレません。
6.ぱそあんのまとめ
ぱそあんのまとめ
- ブランド浸透の第一歩は理念を“行動に翻訳”すること
- 共有は「会議」ではなく「文化」として日常化する
- 新人教育にはブランドマニュアルを活用
- 四半期レビューや表彰制度で仕組み化すると継続しやすい
次回シリーズ予告(98:地域から愛される“共感ブランディング”)
次回は、地域社会とつながりながらブランドを育てる共感ブランディングについて。 広告ではなく“共感”で広がる医院づくりのポイントを紹介します。