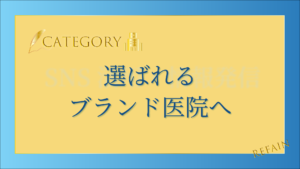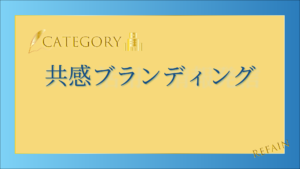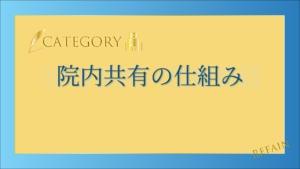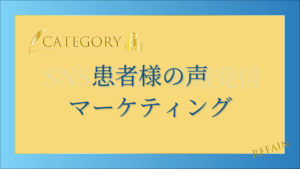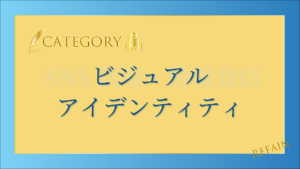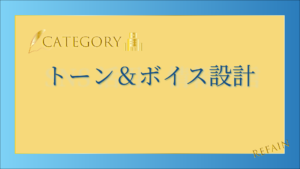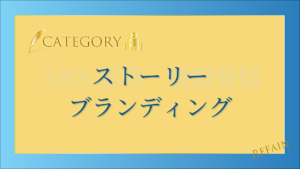1.なぜ監修がブランドに必要なのか
監修とは、医院やメディアの発信内容を専門家が確認・保証する仕組みです。 単なる「チェック」ではなく、「その医院が誠実に正しい情報を発信している」ことを示す証拠になります。
- ① 信頼性の向上:専門家が関与していることで情報の信頼度が上がる
- ② 差別化:監修つきの記事・サイトは他院と一線を画す
- ③ SEO効果:GoogleのE-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を高める
つまり監修とは、ブランドの「信頼の根拠」を示す仕組みそのものです。
2.E-E-A-T時代に求められる「専門家の見える化」
Googleが評価基準として掲げる「E-E-A-T」は、医療ブランディングにも直結します。 特に医療分野(YMYL領域)では、「誰が、どんな資格で、どの立場から」発信しているかが明示されていることが重要です。
| E-E-A-T要素 | 医院での具体化ポイント |
|---|---|
| Experience(経験) | 院長や専門医の実績・臨床経験を紹介 |
| Expertise(専門性) | 専門分野・資格・学会認定を記載 |
| Authoritativeness(権威性) | 監修・取材・メディア掲載実績を表示 |
| Trustworthiness(信頼性) | 透明な情報源・更新日・監修日を明記 |
監修者の肩書や専門分野を正しく記載するだけでも、ユーザーに「信頼して読める」安心感を与えられます。
3.監修の種類と使い分け
監修には、医院内で完結するものと外部専門家を招くものの2種類があります。 目的に応じて適切に使い分けることで、無理のない形で信頼性を高められます。
- ① 院内監修: 院長・副院長が公式記事やSNS投稿を確認・承認する体制
- ② 外部監修: 医師・学会認定医・歯科技工士など外部専門家が監修に参加
- ③ メディア監修: 医療メディア・企業Webの内容を医院が監修する(逆パターン)
いずれの場合も、「誰がどの範囲を確認したか」を記録し、更新日と共に明示するのがポイントです。
4.監修ページを“ブランド資産”として設計する
医院サイト内で「監修者紹介ページ」を設けると、SEO・信頼性の両面で効果が高まります。 単なる肩書き紹介に留めず、「どんな想いで監修に携わっているか」まで掲載しましょう。
| 掲載項目 | ポイント |
|---|---|
| 氏名・資格・所属 | 正式名称で記載し、学会・団体名を省略せずに |
| 専門分野・得意領域 | 医院の診療科目と連動させる |
| 監修コメント | 医院の理念や患者様への想いに共感する一文を添える |
| 写真・署名 | 顔写真と署名があると信頼度が格段に上がる |
こうした情報が整っていることで、「信頼できる医院」という印象を外部に一貫して伝えられます。
5.SNSや広報にも“監修の視点”を
監修の考え方は、Webサイトだけでなく、SNS・動画・チラシなどすべての媒体に応用可能です。
たとえば、SNS投稿でも 「◯◯学会認定医による監修のもとで作成」 「医院スタッフと専門医が共同で制作」 といった一文を添えるだけで、患者様に安心感を与えられます。
広報活動すべてに「確認」「根拠」「誠実性」を通わせることが、医院ブランドを長く守る土台になります。
6.ぱそあんのまとめ
- 監修は“信頼の根拠”を示すブランディング手段
- E-E-A-Tに基づき、専門家の関与を明示する
- 監修ページをブランド資産として整える
- SNS・広報物にも「監修の視点」を浸透させる
次回シリーズ予告(100:地域に選ばれるブランド医院を作る10の視点)
いよいよ最終回。 次回は「地域に選ばれるブランド医院」をテーマに、これまでの全章を総まとめ。 医院ブランディングの全体像を10の視点で再整理します。