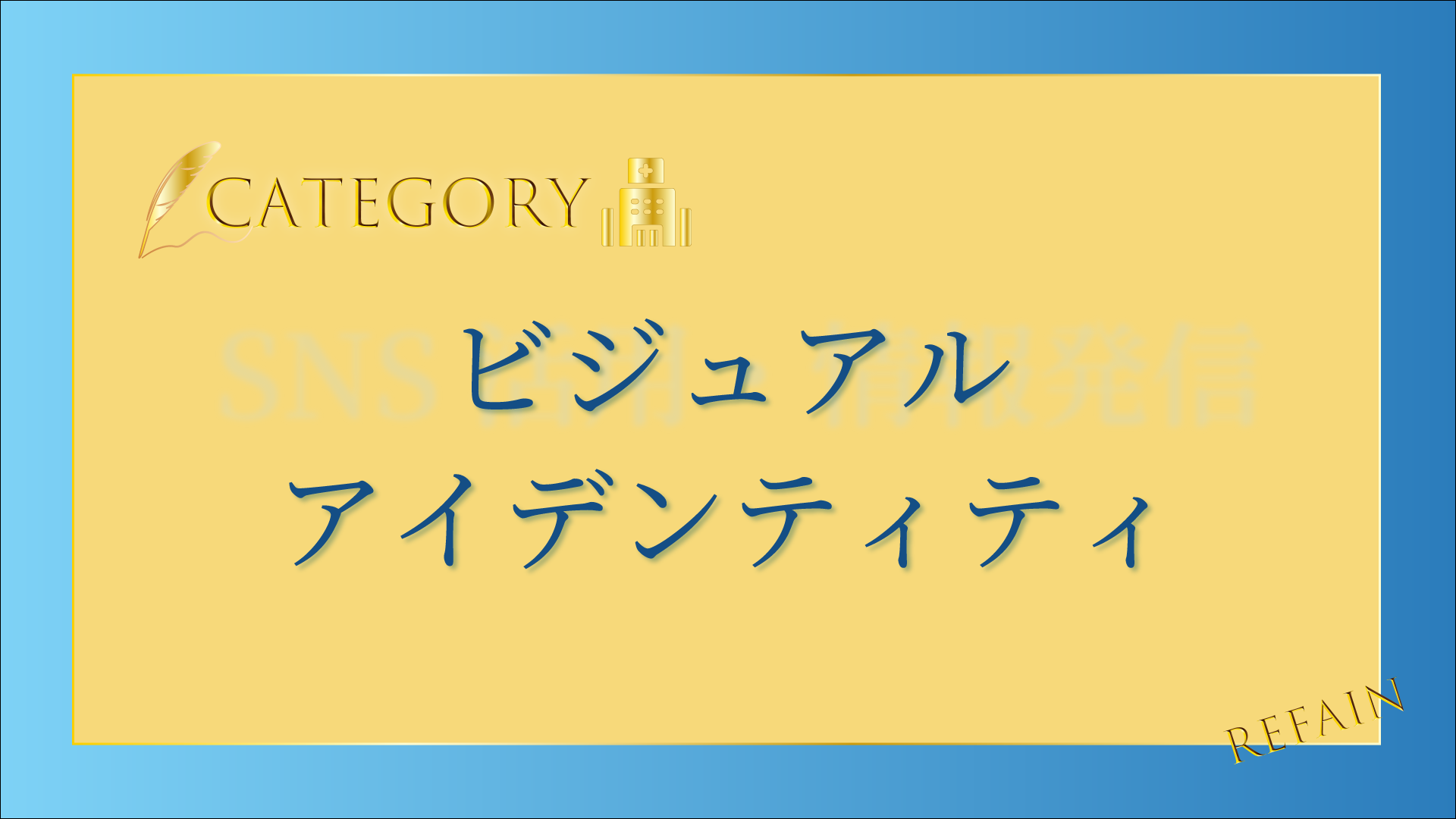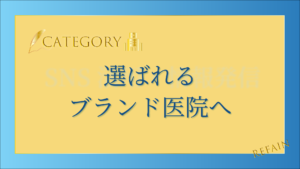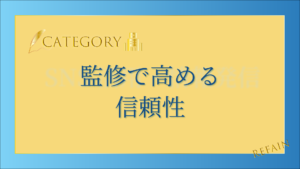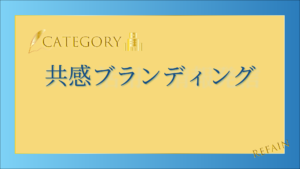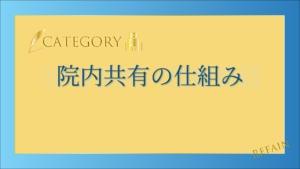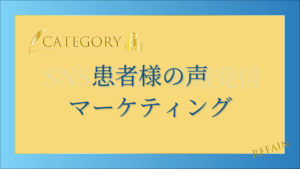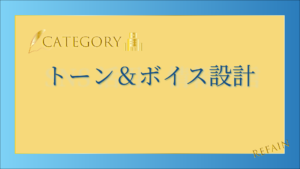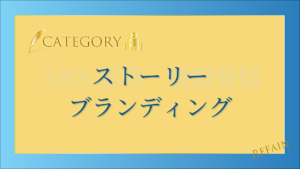1.ビジュアルアイデンティティとは?
ビジュアルアイデンティティとは、医院の理念や想いを視覚的に統一して伝える仕組みのことです。
「言葉でのブランディング」がトーン&ボイスだとすれば、VIは「見た目のブランディング」にあたります。
- ・ロゴ(シンボルマーク、ロゴタイプ)
- ・カラー(メインカラー・サブカラー)
- ・フォント(見出し・本文用の書体)
- ・写真・グラフィック(世界観を統一する素材)
- ・レイアウト(余白・比率・デザインルール)
これらを統一的に設計することで、どの媒体でも“この医院らしい”とすぐにわかる印象をつくることができます。
2.ロゴは“理念の象徴”として設計する
医院ロゴは、単なるデザインではなく理念を視覚化した象徴です。
「何を大切にしている医院か」をシンボルで表現することで、初めて見る人にも理念の方向性が伝わります。
たとえば、 ・家族を表す円やハートのモチーフ ・信頼や清潔感を感じるブルー系カラー ・先進性を感じるシンプルな線や形 といった要素を組み合わせると、医院の“人柄”がデザインから感じ取れます。
重要なのは、「見た目の好み」ではなく「医院の軸」から作ること。
理念を視覚的に翻訳することが、ブランディングデザインの第一歩です。
3.カラーは“感情”を設計する
色は、患者様の印象に最も強く影響します。
清潔感や安心感を与えるブルー系、やさしさや温もりを感じるベージュ・ピンク系など、医院の個性に合わせて「感情」を設計しましょう。
| カラー | 印象・心理効果 | おすすめ医院タイプ |
|---|---|---|
| ブルー | 清潔・誠実・安心 | 内科・歯科・整形外科など |
| グリーン | 自然・癒し・調和 | 小児科・予防歯科・整体系 |
| ピンク | やさしさ・親しみ・思いやり | 小児歯科・婦人科など |
| ゴールド | 高級感・専門性・自信 | 審美歯科・美容医療など |
また、メインカラーとサブカラーを決める際は、「色の使い方ルール」(例:背景80%、アクセント20%)を設定しておくと、媒体間のブレを防げます。
4.フォントと写真で“医院の空気感”を伝える
フォントは医院の人格を表します。 角が丸い書体はやさしい印象、明朝体は誠実で品のある印象、ゴシック体は安定感を感じさせます。
写真もまた、トーンの統一が大切です。
たとえば、自然光を活かした撮影・白を基調とした背景・笑顔のスタッフカットを揃えるだけで、医院の温度感が伝わります。
フォント・写真・レイアウトが調和すると、「見るだけで安心する」ような医院サイトが完成します。
5.VIを“資産”として運用する
VIは一度作って終わりではなく、医院の成長とともに進化させていくべきものです。
新しい診療科の追加やリニューアル時には、既存のデザインルールと照らし合わせて更新しましょう。
- ・ロゴ・カラー・フォントの使用ルールを明文化
- ・スタッフやデザイナーと共有する「ブランドブック」を作成
- ・SNS投稿や印刷物にも同じ基準を適用
- ・変更時は“理念との整合性”を必ず確認
こうして積み重ねることで、患者様が無意識のうちに「この医院=信頼できる」と感じるブランド資産が育ちます。
6.ぱそあんのまとめ
- ビジュアルアイデンティティは医院の理念を“見える形”にする仕組み
- ロゴ・カラー・フォントで医院の世界観を統一
- 色は「感情」、フォントは「人格」、写真は「温度」を伝える
- ルールを明文化して継続運用することがブランド資産を育てる
次回シリーズ予告(96:医院ブランディングを支える“患者様の声マーケティング”)
次回は、実際の“患者様の声”を活用して信頼を高めるレビュー・体験談マーケティングを解説します。
第三者視点の信頼構築が、ブランドをより強く支える鍵になります。