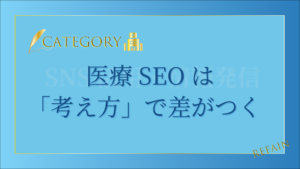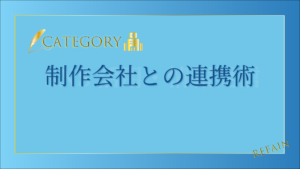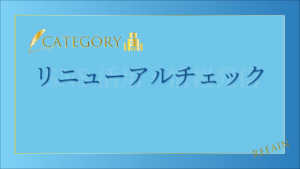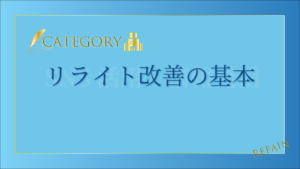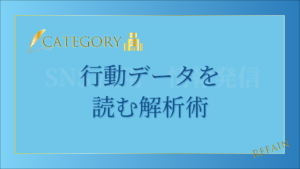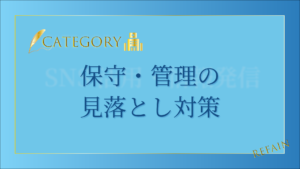1.ガイドラインの目的を正しく理解する
 院長
院長ぱそあん先生、そもそも医療広告ガイドラインって“何を規制する”ためのものなんですか?



目的は「患者様の誤認を防ぐこと」です。
つまり、“正確な情報提供”をすることが一番のルール。
過度な表現や誇大広告を禁止し、「安心して医療を選べる環境」を守るための指針なんです。
- ① 虚偽・誇大な表現を使わない
- ② 客観的根拠のない優位性を示さない
- ③ 体験談・症例写真はルール内で使用する
2.“使ってはいけない表現”を理解しておく



どんな表現がNGなんですか?気をつけるポイントを知りたいです。



NG表現の多くは「断定」や「誤認」を招く言い回しです。 また、“ビフォーアフター写真”や“口コミ誘導”も注意が必要です。
- ・「必ず治ります」「完全に痛みが取れます」などの断定表現
- ・「地域で一番」「最新」「日本初」などの比較・誇張表現
- ・「痛くない」「短期間で治る」など根拠のない表現
- ・体験談・口コミを広告ページ内に掲載する
- ・ビフォーアフター写真を説明なしで掲載する
ポイントは「読者が“必ずそうなる”と誤解しないか?」を常に意識すること。 安心を伝えるつもりが、誇張に見えてしまうこともあります。
3.“伝わる表現”に言い換えるテクニック



でも、魅力を伝えるにはある程度強調したいんです…。表現の工夫ってありますか?



もちろんあります。
NGを避けながらも、「事実+根拠+患者様の安心」を軸に書くことで、十分に魅力を伝えられます。
- ❌「痛くない治療です」 → ✅「麻酔や説明を工夫し、痛みを最小限に抑えています」
- ❌「最短で治ります」 → ✅「できるだけ通院回数を減らせるよう努めています」
- ❌「地域No.1」 → ✅「地域の皆様に長くご利用いただいています」
“断定”ではなく、“姿勢”を示すこと。 そのほうが誠実で信頼される印象になります。
4.症例写真・体験談のルール



ビフォーアフター写真って全部NGなんですか?



いいえ、条件を満たせば掲載可能です。 厚生労働省のガイドラインでは、以下の3条件を満たせば使用できます。
- ① 治療内容・費用・リスクなどを正確に明記している
- ② 写真が特定の患者を特定できないよう配慮されている
- ③ 結果がすべての人に当てはまる表現ではないことを明示している
また、体験談(口コミ)は広告ページ内に掲載不可ですが、独立した「患者様の声ページ」やGoogleビジネスプロフィールなどで紹介するのはOKです。
5.ページ構成に落とし込むポイント



実際のページ構成で、ガイドラインを意識するときのコツはありますか?



以下のように、“事実”と“感情”を分けて構成すると安全で伝わりやすいページになります。
- ① 「治療の流れ」…事実説明(誰が・何を・どう行うか)
- ② 「特徴・工夫」…取り組み姿勢(医院の想い・工夫)
- ③ 「よくある質問」…安心補足(リスク・回数・費用)
感情訴求と根拠提示を分けることで、誇張と誤解を防ぎながら“誠実な魅力”を伝えられます。
6.SEO・ブランディングとの両立
ガイドライン対応は“制限”ではなく、“信頼を高める設計”です。 誠実で明確な情報ほど、Googleの評価(E-E-A-T)でもプラスになります。 結果的にSEO・ブランディング両方の効果を得られます。
- ・Experience(経験):院長の実績・資格を明記
- ・Expertise(専門性):専門領域の説明を具体的に
- ・Authoritativeness(権威性):学会・認定などの正式名称を表記
- ・Trust(信頼):リスク・費用・通院回数を正確に掲載
7.ぱそあんのまとめ
- 医療広告ガイドラインは「安心を守るルール」
- 断定・誇張・比較表現を避け、事実+根拠で伝える
- 症例写真は3条件を満たせば安全に掲載できる
- 「感情」と「事実」を分けた構成で誠実な印象に
- E-E-A-Tの4要素を整えればSEOにも強くなる
“ルールを守ること”は、“信頼を積み重ねること”。 正しく伝えるサイト設計が、長く選ばれる医院の基盤になります。
次回記事のお知らせ(B6️⃣ 医療法人・個人医院で異なるサイト構成の考え方)
次回は、医療法人と個人医院の違いによるサイト構成の最適化を紹介します。 医院の規模・方針に合わせたメニュー構成と情報設計のコツを解説します。