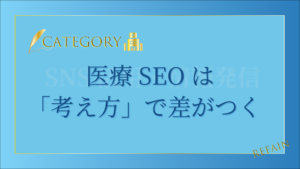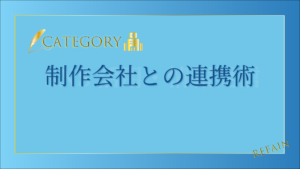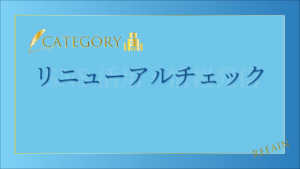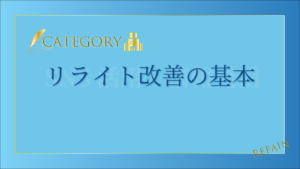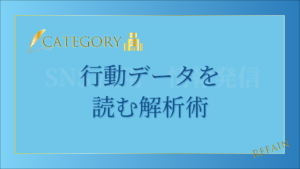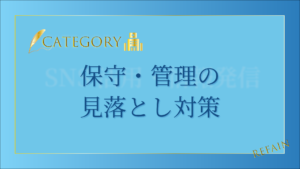1.E-E-A-Tとは?4つの視点を理解する
 院長
院長ぱそあん先生、そもそもE-E-A-Tって何の略なんですか?SEOでよく聞くけど…



E-E-A-Tは、Googleが医療・法律・お金などの「専門領域サイト」を評価する4つの基準です。 次の4つの要素を満たすことで、信頼されるコンテンツになります。
- E:Experience(経験) ― 現場での経験・症例・実例を示す
- E:Expertise(専門性) ― 医学的根拠・専門的知識をわかりやすく伝える
- A:Authoritativeness(権威性) ― 所属学会・資格・監修者の明記
- T:Trust(信頼性) ― 正確な情報源・引用・更新日を記載する
医療コラムでは「信頼できる医療情報を届ける」ことが最優先。 E-E-A-TはSEOだけでなく、患者様からの信頼にも直結します。
2.E-E-A-Tを高める“テーマの選び方”



テーマはどう選べばいいんですか?よくある症状の記事だけじゃダメですか?



「症状解説」も大事ですが、それだけでは専門性が伝わりにくいです。 経験(E)や医院の想いを交えたテーマにすることで、他院との差別化につながります。
- ① 日常と結びつく症状解説(例:冷たいもので歯がしみるのはなぜ?)
- ② 医師の経験をもとにした解説(例:親知らず抜歯でよくあるトラブル)
- ③ 患者様の不安を解消するテーマ(例:インプラントは怖い?手術の流れを解説)
- ④ 季節・トレンドに合わせた話題(例:花粉症と口呼吸の関係)
- ⑤ 誤情報を正すテーマ(例:ホワイトニングで歯が溶けるって本当?)
「検索されやすい×医院の専門性が活きる」テーマを意識して選ぶと、自然にE-E-A-Tが高まります。
3.“体験”と“専門性”を融合させる構成術



経験と専門性、どうやって両方を出せばいいですか?



ポイントは、「実際の診療エピソード」→「専門解説」→「まとめ」の流れにすることです。 ストーリー+根拠の両方を持たせると、読者も理解しやすく信頼が増します。
- ① 導入:患者様のよくある悩み・質問
- ② 事例:実際にあったケース(※個人情報に配慮)
- ③ 解説:原因・治療法・予防法を専門的に説明
- ④ まとめ:医院としての考え方・アドバイス
この構成はE-E-A-Tすべてを自然に含める形。 経験(E)と専門知識(E)が合わさることで、唯一無二の内容になります。
4.引用・監修で「権威性」「信頼性」を補強する



引用や監修って、どれくらい必要なんですか?



医学情報は常にアップデートされるため、信頼できる外部情報源を併記することが大切です。 出典を明示することで、Googleと読者の両方から信頼されます。
- ・厚生労働省・日本歯科医師会などの公式情報
- ・大学病院・専門学会のガイドライン
- ・院長・専門医による監修表記(例:監修:〇〇歯科 院長 〇〇先生)
- ・記事の更新日・監修日を明示
出典をつけるだけで、「根拠のある記事」という印象になります。 SEOにもプラスに働く重要な要素です。
5.読まれる医療コラムに共通する3つの要素
- ① 導入で「自分のことかも」と思わせる身近な書き出し
- ② 図解・見出しで視覚的に理解しやすくする
- ③ 医院の考え・アドバイスを「やさしい言葉」で伝える
医療コラムは「検索のため」ではなく「安心のため」に書く。 この視点を持つことで、自然と信頼とSEOの両方が伸びます。
6.ぱそあんのまとめ
- E-E-A-Tは「経験・専門性・権威性・信頼性」の4要素
- 症状解説だけでなく“体験+専門性”を融合させる
- 構成は「事例→専門解説→まとめ」が鉄板
- 出典・監修・更新日を明示して信頼性を担保
- 読者目線のやさしい言葉で安心感を与える
E-E-A-Tを意識した医療コラムは、SEOだけでなく「医院の信頼ブランド」を作ります。 “検索で見つけられる医院”から、“信頼で選ばれる医院”へ育てていきましょう。
次回記事のお知らせ(B8️⃣ Googleマップと口コミを活かすサイト設計)
次回は、Googleビジネスプロフィールと口コミを活かした集患設計について。 信頼を可視化する“外部導線”の作り方を紹介します。